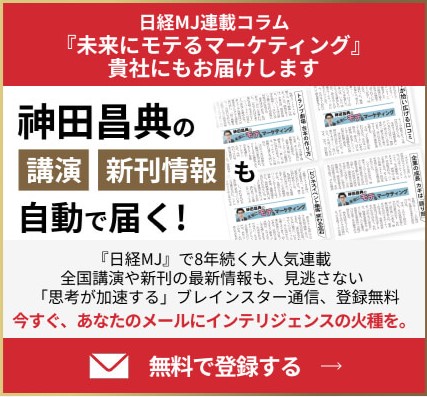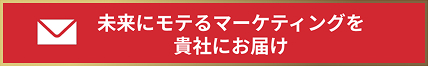新着情報

ホラクラシー組織とは?特徴や導入する際の課題などわかりやすく解説
環境変化の激しい現代では、ホラクラシー組織への関心が高まっています。
従来の階層型組織では変化への対応が難しく、意思決定の遅れによってビジネスチャンスを逃してしまう課題が指摘されているからです。
ホラクラシー組織は、役割ベースの柔軟な組織運営を通じて、意思決定のスピードを向上させ、環境変化に素早く対応できる組織が構築できます。
ただし、実際の導入では、従来の組織文化からの転換や新しい運営ルールの整備が必要となります。
多くの企業がこの新しい組織形態に注目する中で、その具体的な特徴や実践方法については、まだ十分な理解が広まっていないのが現状です。
本記事では、ホラクラシー組織の基本的な考え方から特徴、さらには導入時の課題まで、詳しく解説していきます。
ホラクラシー組織の内容を把握し導入を検討したい方は、ぜひ参考にしてください。
ホラクラシー組織とは?
近年、従来のヒエラルキー型組織からの脱却を目指す企業が増えています。
その中で注目を集めているのが「ホラクラシー組織」です。
ホラクラシーとは、ギリシャ語で「全体」を意味する「ホロス(holos)」と、組織の統治方法を表す「-cracy」を組み合わせた造語です。
従来の上下関係を重視した組織構造から離れ、権限や役割を分散させた新しい組織モデルを指します。
このような組織形態が生まれた背景には、市場環境の急速な変化があります。
従来の指揮命令系統では、変化への対応が遅くなりがちでした。
そこで、より柔軟で迅速な意思決定を可能にする組織の形が求められるようになりました。
例えば、製品開発部門で新しいアイデアが生まれた場合、従来の組織では上司への報告や承認プロセスに時間がかかっていました。
しかし、ホラクラシー組織では、各チームや個人に権限が委譲されているため、自律的に判断し、素早く行動に移せます。
ホラクラシーの概念は、2007年にブライアン・J・ロバートソンによって正式に体系化されました。
組織運営の具体的な方法を定めた「ホラクラシー憲法」も作られ、多くの企業で実践されています。
ホラクラシー組織は、従来の上下関係による管理から、役割と責任に基づく自律的な運営へと転換を図る組織モデルといえます。
環境変化に素早く対応し、個々の主体性を活かした組織づくりを目指す企業にとって、有効な選択肢となるでしょう。
参考:金沢大学先端科学・社会共創推進機構「タテ社会からの脱皮」
ホラクラシー組織と他の組織モデルとの違い
ホラクラシー以外にも、さまざまな組織モデルがあります。
ここでは、以下の2つの組織モデルとホラクラシー組織の違いを見ていきましょう。
ティール組織との違い
ホラクラシー組織を理解する上で、よく比較されるのが「ティール組織」です。
両者は一見似ているように見えますが、その本質や目指す方向性には違いがあります。
ティール組織は、ホラクラシー組織と同様に自律性と柔軟性を重視しますが、より包括的な組織の発展段階を示す概念です。
ティール組織の特徴は、「エボリューショナリーパーパス」「ホールネス」「セルフマネジメント」の3つの重要な要素が備わっています。
3つの主な内容は、以下のとおりです。
|
エボリューショナリーパーパス |
|
|
ホールネス |
|
|
セルフマネジメント |
|
このように、ティール組織は組織の「あり方」や「価値観」に重点を置くのに対し、ホラクラシー組織は具体的な「仕組み」や「ルール」を重視します。
ホラクラシー組織が明確な運用ルール(ホラクラシー憲法)に基づいて運営されるのに対し、ティール組織はより柔軟で有機的な発展を目指します。
両者の違いが理解できれば、自社に適した組織モデルの選択がしやすくなるでしょう。
組織の現状や目指す方向性に応じて、より適切な形を選ぶことが大切です。
ヒエラルキー型組織との違い
ホラクラシー組織の特徴をより理解するために、従来型の「ヒエラルキー型組織」との違いを見ていきましょう。
ヒエラルキー型組織とは、役職や職位による階層構造を持つ組織形態です。
一般的な日本企業の多くがこの形態を採用しており、上司が部下に指示を出し、部下がそれに従う明確な指揮命令系統が特徴です。
両者の主な違いは、以下の点にあります。
|
ヒエラルキー型 |
ホラクラシー型 |
|
|
意思決定プロセス |
上層部の承認が必要 |
権限が分散され、各役割で判断 |
|
組織構造 |
固定的な階層構造 |
柔軟なサークル制 |
|
権限と責任 |
役職に応じて集中 |
役割に応じて分散 |
これらの違いは、実務での意思決定のスピードや柔軟性に影響を与えます。
例えば、新規プロジェクトの立ち上げを考えた場合、ヒエラルキー型組織では複数の承認プロセスを経る必要がありますが、ホラクラシー組織では担当サークルが主体的に判断できます。
ただし、どちらが優れているというわけではありません。
ヒエラルキー型組織は、大規模なプロジェクトの管理や、品質管理が大切な業務でその統制力を発揮します。
一方、ホラクラシー組織は、イノベーションが求められる場面や、市場の変化に素早く対応する必要がある状況で力を発揮します。
組織の規模や事業内容、さらには業務内容に応じて、適切な組織形態を選択できるようにすると良いでしょう。
ホラクラシー組織の目的
現代のビジネス環境では、従来の階層型組織から脱却し、より柔軟で自律的な組織運営を実現する「ホラクラシー組織」に注目が集まっています。
このような組織形態が必要とされる背景には、デジタル化の進展や市場ニーズの多様化があります。
従来の指揮命令系統では、これらの変化に迅速な対応が難しくなってきたからです。
ホラクラシー組織の具体的な目的には、以下のようなものが挙げられます。
|
意思決定の迅速化 |
|
|
組織の透明性向上 |
|
|
メンバーの主体性強化 |
|
|
持続的な改善と適応 |
|
例えば、新規プロジェクトの立ち上げ時には、各メンバーが自身の役割に基づいて主体的に動き、アイデアを即座に形にできます。
組織全体の透明性が高まることで、部門間の連携もスムーズになるでしょう。
ホラクラシー組織は、現代のビジネス環境で求められる迅速な意思決定と高い適応力を実現し、従業員のエンゲージメント向上にもつながります。
組織の持続的な成長を目指す企業にとって、有効な選択肢となるはずです。
ホラクラシー組織の主な特徴
ホラクラシー組織が注目を集める理由は、その特徴的な組織運営の仕組みにあります。
従来の組織とは異なる独自の特徴を持つことで、環境変化への対応力を高め、メンバーの主体性を引き出しやすくなります。
ホラクラシー組織の主な特徴は、以下のとおりです。
- フラットな組織構造
- 自律的な意思決定と役割分担
- 個々の意見を活かす仕組み
- ホラクラシー組織の役割
それでは、ホラクラシー組織の具体的な特徴を詳しく見ていきましょう。
フラットな組織構造
ホラクラシー組織の特徴的な要素が、フラットな組織構造です。
従来の組織でみられた階層的な役職や地位による上下関係を廃し、全てのメンバーが対等な立場で意見を出し合える環境を作り出します。
このような構造が求められる背景には、従来の階層型組織での意思決定の遅さや、コミュニケーションの非効率さがあります。
フラットな組織構造では、直接的なコミュニケーションが可能となり、アイデアや情報の共有がスムーズにできるでしょう。
フラットな組織構造であることのメリット・デメリットには、以下のようなものが挙げられます。
|
メリット |
デメリット |
|
|
フラットな組織構造を効果的に機能させるためには、明確なルールとプロセスの設定が必要です。
特に、意思決定の方法や責任の所在を具体的に定め、メンバー全員が理解していなければなりません。
フラットな組織構造は、適切な運用により組織の俊敏性と創造性を高めてくれます。
ただし、その実現には慎重な準備と継続的な改善が欠かせないでしょう。
自律的な意思決定と役割分担
ホラクラシー組織のもう一つの特徴が、自律的な意思決定と柔軟な役割分担です。
従来の職務記述書による固定的な業務範囲から脱却し、状況に応じて柔軟に役割を変更できる仕組みを採用しています。
このような仕組みの中心となるのが「役割(ロール)」の考え方です。
一人のメンバーが複数の役割を担当でき、それぞれの役割に応じた意思決定権を持ちます。
役割に基づく意思決定の特徴には、以下のようなものが挙げられます。
- 職務ではなく役割で定義
- 複数の役割を同時に担当可能
- 状況に応じて役割を変更
- 各役割に意思決定権を付与
メンバーは自身の役割の範囲内で、上司の承認を必要とせず自律的に判断を下すことができます。
これにより、業務のスピードが向上し、状況の変化にも柔軟に対応できるようになります。
役割ベースの組織運営により、メンバーの主体性が高まり、組織全体の機動力も向上するでしょう。
ただし、役割と責任の範囲を明確にし、全員で共有する必要があります。
個々の意見を活かす仕組み
ホラクラシー組織では、メンバー一人ひとりの意見を組織の意思決定に活かすためにサークルと呼ばれる小規模なチーム単位で行われる定期的なミーティングを実施しています。
このミーティングでは、業務上の課題や改善案を立場に関係なく自由に意見を出し合うことができます。
プロジェクトの状況に応じて、柔軟にチーム編成を変更することも可能です。
各サークルでの議論は記録され、他のサークルとも共有されます。
そのため、組織全体での知見の蓄積と、部門を超えた協力体制の構築が可能になります。
定期的なミーティングと情報共有の仕組みにより、メンバーの声を組織の改善に活かしやすくなるでしょう。
ただし、効果的な運用のためには、適切な議論の進行役と記録係の存在が必要です。
ホラクラシー組織の役割
ホラクラシー組織では、効率的な運営を実現するために、いくつかの役割が設定されています。
サークル運営での主な役割には、以下のようなものが挙げられます。
|
リードリンク |
|
|
ファシリテーター |
|
|
セクレタリー |
|
これらの役割は固定的なものではなく、状況に応じて柔軟に変更する必要があります。
一人のメンバーが複数の役割を担うこともあれば、役割を交代しさまざまな視点を取り入れることもできます。
このような明確な役割分担により、組織全体の透明性が高まり、効率的な運営が可能となるのが特徴です。
ホラクラシー組織を導入する際の課題
ホラクラシー組織は、その革新的な特徴から多くの企業で注目を集めていますが、実際の導入にはさまざまな課題が存在します。
特に日本企業では、従来の組織文化との違いから、スムーズな移行が難しいケースも少なくありません。
主な課題には、以下のようなものが挙げられます。
- 権限の曖昧さ
- チーム間の連携不足
- 日本における導入の難しさ
それぞれの課題内容を見ていきましょう。
権限の曖昧さ
ホラクラシー組織の導入の課題の一つが「権限の曖昧さ」です。
従来の組織では役職や職位で明確だった権限が、ホラクラシーでは役割ベースとなるため、どこまでの決定権があるのか不明確になりがちです。
この曖昧さは、以下のような場面で特に顕著になります。
- 複数の役割が重なる業務
- 部門をまたぐプロジェクト
- 予算配分に関する判断
- 緊急時の意思決定
この課題に対処するためには、役割ごとの権限範囲を明確に定義し、可視化する必要があります。
例えば、意思決定の範囲や予算執行の権限を具体的に文書化し、全メンバーで共有すれば、不必要な混乱を防げるでしょう。
チーム間の連携不足
ホラクラシー組織では、各サークルが自律的に活動するため、チーム間の連携が不足しがちです。
特にサークル間での情報共有や協力体制の構築に課題を抱えることが少なくありません。
チーム間の連携での主な課題には、以下のようなものが挙げられます。
- 重複した作業の発生
- 全体像の把握不足
- 優先順位の不一致
この課題を解消するためには、定期的なミーティングの開催が効果的です。
例えば、サークル間での情報共有会を設けることで、プロジェクトの進捗状況や課題を共有し、必要な協力体制を築くことができます。
さらに、複数のサークルが関わるプロジェクトでは、共通の目標設定と進捗管理の仕組みを整備しておくといいでしょう。
日本における導入の難しさ
ホラクラシー組織の導入は、日本の企業文化では、特有の課題に直面します。
長年培われてきた日本的な組織運営の特徴が、ホラクラシーの理念と相反する場面が多く見られます。
日本企業における主な課題は、以下のとおりです。
- 年功序列の意識
- 暗黙の了解重視
- 集団的意思決定
- 調和を重んじる傾向
このような特徴を持つ日本企業では、段階的なアプローチが効果的です。
例えば、まずは一部の部門や新規プロジェクトから試験的に導入し、徐々に範囲を広げていくことで、組織文化との軋轢を最小限に抑えられるでしょう。
日本の組織文化の良さを活かしながら、ホラクラシーの要素を取り入れていく柔軟な姿勢が必要です。
まとめ
本記事では、ホラクラシー組織の特徴から導入時の課題まで詳しく解説してきました。
環境変化が激しい現代で、ホラクラシー組織は従来の階層型組織に代わる新しい選択肢として注目を集めています。
しかし、実際の導入には慎重な検討が必要です。
権限範囲の曖昧さやチーム間の連携不足、さらには日本企業特有の文化的な課題など、克服すべき点も少なくありません。
特に運用ルールの整備は、円滑な組織運営のために欠かせない要素となります。
ホラクラシー組織の導入を検討する際は、自社の状況や文化に合わせた段階的なアプローチが大切です。
一度にすべてを変えるのではなく、部分的な導入から始めて徐々に範囲を広げていくことで、より自然な組織変革が実現できるでしょう。
これからの時代に求められる組織の形は、環境の変化に応じて進化し続けるものです。
ホラクラシー組織の考え方を参考に、自社に最適な組織づくりを目指してみてはいかがでしょうか。
そこでもし、ホラクラシー組織に関する疑問や質問のある方は、いつでもアルマ・クリエイションにご相談ください。貴社に最適なソリューションを提供いたします。
インサイト
動画公開中
次の10億、100億を見据えるなら──
「キラーパス」は
未来から逆算して見えてくる
【ミニ講座】フューチャーマッピング
なぜこんなに、うまくいくのか
事例と仕組み
(視聴時間:約15分/音声だけでも理解できます)
▶ 今すぐ無料で視聴